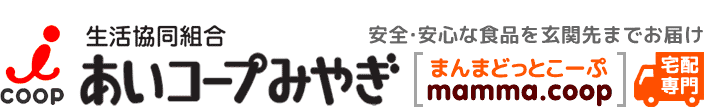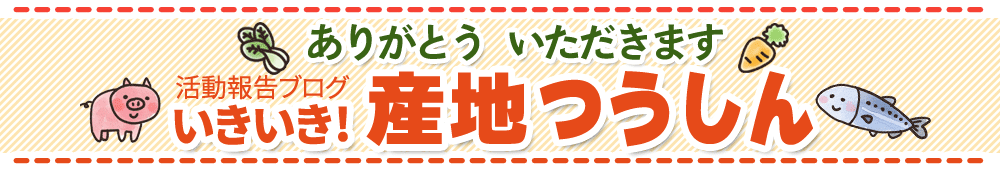6月に入り、夏らしくなってきました。
「前回、花を摘んだりんごの木がどうなっているか?」りんごのオーナーたちが、今回も興味津々で天童に集合。今回は8家族25名の組合員と、職員の学習活動「コアサイクル活動」に参加の職員ら6名が汗を流します。

お母さんと一緒に作業
花摘みから一か月以上が経ち、大きな梅の実のように膨らんだりんごが木についていました。

真剣な表情で生産者に教わる参加者
枝の先にひとかたまりになっている実たちの中から、歪でなく中心から均等に膨らんだものを残して周りの実を落としていきます。

摘果前
花摘み同様、なんとも惜しい気持ちになりますが、大きな美味しい実を育てるための大事な作業です。

摘果後

高いところも注意しながら挑戦
今回はその他に、「フェロモン製剤」を木に設置する作業もしました。
「フェロモン製剤」は、木に吹きかけたりする農薬ではなく、虫が「もう繁殖期を終えました」と感じるフェロモンを発生することで虫たちが勘違いし、繁殖を抑制する、つまり虫が世代交代するのを抑える効果があるグッズだそうで、ネオニコチノイド系農薬なしで、且つ他の成分も押さえているこの園地では期待のアイテムです。

コンフューザーで虫を増やさないための対策
匂いを付けた細いバンド状のものを枝に付けるだけで、作物に影響はないとのこと。
そしてもう一つ。木に棲みついたアブラムシ「ワタムシ」をバーナーで焼くこともしました。

バーナーでワタムシ焼き
ちょっと残酷な感じもしましたが、安全な食べ物を得るためにはこんな作業もいるのだなと感じながら、木に炎を当てました。
子供たちを中心に、園地にどんな虫がいるか生き物調べもして、いったん園地を離れます。
今度は、春先の霜の害で実をつける事ができなかった園地へ一同移動です。

霜の被害について説明する生産者
オーナーの園地は僅かな海抜の差で被害を免れたと聞いていますが、実際に被害のあった園地へ行って騒然。
まず、今の時期宝石のように鈴なりになっているさくらんぼが、ぽつりぽつりとしか実っていません。さっきあんなに摘花したりんごも、木の上の方に少しあるだけ。これでは生産者は暮らしていけないでしょう。
「果樹農家にとっては、冬を越え7か月振りの収入となるはずのサクランボ。これでは収入にならないが、来年のことを考えると防除、消毒を怠ることはできず、収入は生まないが手間暇はかかり費用もかかる」とおっしゃる生産者の片桐さんのお話を、参加者は聞き入っていました。
今回の園地での作業は、りんごづくりのお楽しみを体験しつつ、農家の厳しい現実も目の当たりにした、学びの多い活動となりました。
(担当理事)